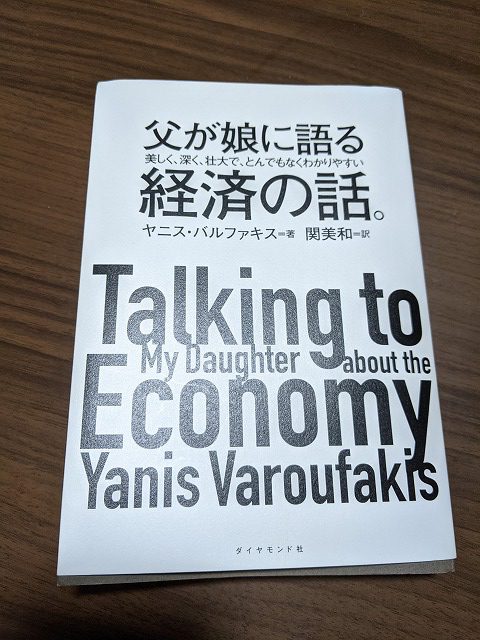ヤニス・バルファキス氏の名著「父が娘に語る経済の話」を読んだので、今回はその感想と書評を述べていきます。
この本では、前半部分では通貨の起源、貧困や格差が生まれる原因、銀行や国家の成り立ちや役割が書かれています。
経済学を学んだことがない僕にとっては、それらは非常に勉強になりました。
しかし、それよりも印象に残ったのは後半部分で書かれている内容です。
後半では、市場経済の闇の部分というか、普段僕たちが見て見ぬふりをする部分にスポットを当て、このままでは市場経済、ひいてはこの世界がどうなるのかを考えさせられました。
そこで、個人的見解として有意義だったと思える点を、感想及び意見を語らせていただきたいと思います。
父が娘に語る経済の話 重要な点
さて、この本で語られていて重要だと思った点は、「市場経済そのもの」のデメリットを挙げているという点です。
そもそも、市場経済とは、超簡単に言えば「働いて、買い物をする」という日常的な営みの事です。
では、この当たり前の行動に、どんなデメリットがあるというのでしょうか?
それは、資源を食いつぶす事です。
というのも、僕たちが働いて、商品を生みだすために必要なものは何でしょう?
それは動物や環境といった資源です。
動物を飼育したり殺したり、森林伐採や都市開発、石油を掘り起こす事で、僕たちは商品を作って売っているのです。
市場経済では、その勢いは止まる事はなく、むしろが競争が加速し続ける事によって、資源を奪いつくしてしまうのです。
その例として、この本で語られているのは、オーストラリアの先住民であるアボリジニがイギリスによって支配される過程が挙げられます。
そこには、「貧しいもの」は「豊かなもの」から根こそぎ奪っていくという構図が描かれていました。
そもそも、アボリジニには、広大な土地と豊かな資源があったため、そもそも発展する必要がありませんでした。
しかし、逆に気候や環境に恵まれなかったイギリスは、人間が「生産」し「貯蓄」する必要がありました。
そのためイギリスでは農耕が発達し、貯蓄することによって貧富の差が現れるようになっていくのです。
こうしてイギリスはその文化により発展を続けると共に、資源を持つものから富を奪うようになりました。
その結果が残酷な植民地支配となったというのです。
さらには、イギリスは工場の囲い込みなどで貧困層を生み出し、利益追求によって多くの悲劇を生むこととなりました。
そしてこの教訓は、現代の地球に当てはめても同じことが言えます。
地球という豊かな資源があり、それを僕たち人間たちが奪っていく、という構図は支配や略奪と同じ事なのです。
そして、利益追求によって労働者たちに格差や貧困が生まれるのも、現代に通じるところがあります。
環境問題は陳腐なのか?
しかし、そう言うと「そんなの分かり切った事でしょ」とも思うかもしれません。
資源やらエネルギー問題や食糧問題など、地球規模での社会問題は山積みなのは、今に始まった事ではないでしょう。
僕としても、「なんだ、そんなのニュースでもよく言ってる危機じゃないか」という感想に行きつきました。
とはいえ、僕はその問題についての関心はあっても、「どうしようもない事だ」とも思っていました。
人間とは愚かなものであり、全てを失わない限り、その破壊活動に終わりはないと思っていました。
しかし、この本ではそんな悲観的な僕に対し、1つの望みを提示してくれました。
それは「民主主義」という唯一の防衛策です。
この本のだいぶ最後のページに書かれていたのですが、ここに作者のメッセージ性を特に感じました。
次は、それをご紹介したいと思います。
民主主義とは何か?
この本で訴えられている「民主主義」とは何でしょうか?
それは、他でもない僕たち1人1人が考える事にあります。
それは何となくの「民主主義」ではなく、「本来の民主主義」の姿です。
というのも、もし、今後企業があらゆる資源を支配するようになったらどうなるでしょうか?
企業は「資源を有効活用する」という名目で、株主や金持ちにとっては良い環境を提供することになるでしょう。
その一方で、力もお金も持たない人は、発言権もなく、ただ富裕層の言いなりとなる世界にもなりえるかもしれません。
考える力すらない人は、そういった権力者に操られるだけでその一生は終わってしまうでしょう。
しかし、もし、1人1人が発言権を持てる社会、すなわち民主化している社会であれば、そんな格差社会に「NO」を突き付ける事が出来るというわけです。
今の日本は、本当に「NO」と言えるのでしょうかね。
ただし、作者は「民主主義」が最もいいと言っているわけではなく、腐敗しやすいとも言っています。
それでも、唯一マシな方法が、民主主義と言うだけの話、という書き方をされていました。
もちろん、僕も政治が介入すれば万事解決ではないと思っています。
問題とは永遠になくならないからこそ問題でなのであり、それが発生するたびに僕たちは考え続けなければならないのでしょう。
中には、政治家に任せれば良いとか、考えるのが面倒くさいとか、他人任せにしたいと思う人もいるかもしれません。
しかし、それを他人任せにしたら、相手から支配されても略奪されても、何も文句は言えなくなります。
政治を作っているのは、僕たち国民1人1人なわけですから、僕たちが考えず、誰が考えるというのでしょうか?
そして、より良い政治にするためには「考える事」と「投票する事」に力を入れる必要があるといえるわけです。
ですので、この本を読んだとき「悲観だけでなく、僕でも何か出来ることがあるんだ」という事を、少なからず実感することが出来ました。
経済学への非難
さて、僕はこの本で特に面白かった点もあり、それもやはり後半の方に書かれていました。
それは、「経済学者」という存在を、あたかも占い師、または哲学者と同列としている点でした。
なぜなら、経済学者は答えを出せないし、その答えが合っているかどうかも証明することが出来ないからです。
いうなれば、哲学者が「答えのない問い」を考えるように、経済学者も「答えのない問い」の正解を求めているというのです。
また、経済学者は「答えを出せない理由を説明するための答え」を作り出すとも書かれています。
それは、占い師が「占いが外れた理由」を考えて、その理由に「説得性」を持たせようとしているのと同じだと言っているのです。
経済学を教える身である著者が、経済に対して非難めいたことを言うのは、非常に興味深い事でした。
僕はこれを読んだとき、もし著者の言う通り、経済学が「哲学」や「占い」のように、確実でないものだったら、学ぶ意味はないのでは?とも思いかけました。
しかし、僕は「では、そこから何を学ぶのか?」という事がより重要なのだと思いました。
そう考えると、経済学は、専門用語だのモデルだのをつらつら学ぶよりも、よほど面白いものを感じざるをえません。
また、そういった面倒なものをすぐに専門家任せにするのではなく、むしろ僕のような素人が考えなければいけない分野であるという事も、この本からは学べました。
父が娘に語る経済の話 感想
では、最後になりますが、総評を述べたいと思います。
さて、まず僕がこの本を手に取ったのは、まさに経済に興味があったからでした。
僕の生活は経済で成り立っているのに、その事を知らないのはいかがなものかと常日頃から思っていたからです。
一応、以前僕は別の経済の本をさらっと読んだことがありましたが、「お勉強」としての知識は書かれていても、実になる事はほとんどありませんでした。
しかし、この本では「経済の起源」そして、「哲学としての経済」が語られていて、視野が広がる感覚を覚えました。
ただし、裏を返せば、ただの勉強の為に学ぶのであれば、この本はほとんど役には立たないでしょう。
ましてやほとんど経済用語が出てこないのですから、なおさらでしょう。
また、「明確な答えが欲しい」と言う人にも不向きと言えます。
お金を儲ける方法だとか、経済を利用したいと考える人は、ガッカリすること間違いなしです。
そういったお金儲けをするような人を非難するような文面も多々あるからです。
では、この本はどんな人に向くのでしょうかか?
それは、哲学を学ぶように「自分に問いかける事に重きを置く人」です。
そういう人は、これを読んだ後、少なくとも読む価値があったのではないかと思われます。
僕としても、この本を読んで、改めて「働く事」や「社会の問題」に目を向ける事ができました。
そして、「自分が出来る事をやろう」と、再び認識させてくれる事となりました。
過去は変えられませんが、未来を作るのは紛れもなく今なのですから、今の人間たちがどう動くのかを、その一員として考えるほかないのでしょう。
というわけで、今回の書評はおしまいとなります。
皆様のご参考になれれば幸いです。